はじめに
この配合理論は、あくまで個人的見解です。
そして、この個人的見解をまとめる上で、大変参考になったものが下記の本になります。
強い父母を配合させるが基本
遺伝学から紐解く
まず遺伝学的な話を。
1本の染色体には様々な遺伝子が含まれていて、毛色や臓器、筋肉などが作られる設計図となる。
その染色体は、馬には64本(32対)あり、父から32本、母から32本を受け継いでいる。
その組み合わせパターンは無限と言っても良い。
そして、遺伝子には「顕性・潜性」があり、競争能力を高める遺伝子が潜性だった場合は、遺伝子としては保持していても、表に出てこない場合もある。
さらには「エピジェネティクス」と呼ばれる、遺伝子本来の形質が出現しない場合もある。
つまり、親には出現しなかった場合でも孫の代で出現する「隔世遺伝」もある。
遺伝は複雑で難解
上記のことを踏まえると、遺伝のパターンを把握し配合に活かすことは不可能だ。
ただ、非現実的にシンプルに考えると、遺伝的には最強馬と全く同じ遺伝子を持てれば良い。
その可能性を最も高めるのは、強い父である50%の遺伝子と、強い母である50%の遺伝子を受け継ぐことだ。
つまり、最強馬×最強馬が、結局は最高の配合理論と考える。
インブリードはデメリットしかない
次に、競馬ゲームでは強い競走馬を生産するためには常識となった「インブリード」についても考えてみたい。
インブリードについては、下記の仮説を立てている。
・インブリード自体は能力向上に関係がない
・虚弱体質や気性悪化などのデメリットがある
・奇跡の血量と呼ばれる3×4から、デメリットが現れにくくなる。
冒頭に述べたように、配合は「最強馬×最強馬」が基本と考える。
ただ、昔は全体的な競走馬のレベルが低く、強い馬は限られていた。
そういう状況下の場合、必然的に父系にも母系にも同じ最強馬の血が流れてしまう。
つまり、強い馬を生産するためにインブリードが必要なのではなく、
強い馬を生産するためにはインブリードが発生してしまったというただの結果だと考える。
そして、近親配合であるインブリードは、虚弱体質や気性悪化のリスクがある。
そのリスクが低くなってくるのが、奇跡の血量と呼ばれる3x4に血が薄まった時なのだろう。
つまりは、奇跡の血量も、強い馬を生産するためのただの結果だと考える。
繰り返しになるが、
インブリード自体にはメリットはなく、「強い馬同士を配合させる」という目的のために発生した結果にすぎない。
それは、日本競馬の結晶「ディープインパクト」が
5代遡ってもインブリードが発生していない、アウトブリード血統であることと合致する。
距離適性は関係がない
スプリンターもステイヤーも全て「中距離」
まず、1000mと3000mでは大きな違いがあるように思える。
しかし、競走馬にとってこの距離は、全て人間でいうところの「中距離」に該当する。
JRA競走馬総合研究所が、レース距離別にエネルギー消費の内訳を調べている。
■無酸素エネルギー、□有酸素エネルギー
短距離(1000m)
■■■■□□□□□□(40%,60%)
中距離(16~1800m)
■■■□□□□□□□(28%,72%)
長距離(25~3000m)
■■□□□□□□□□(20%,80%)
長距離になればなるほど、有酸素エネルギーが多くなっている。
しかし、この数値は人間陸上競技では、全て「中距離」のカテゴリになる。
スプリンターとステイヤーと聞くと
短距離ランナーとマラソンランナーの違いぐらいあると思っていたが
実際は、800Mランナーと1500Mランナーぐらいの違いということらしい。
800M走と1500M走の違いから考える、競走馬の距離適性
中学時代に陸上部だった妻に800Mと1500Mの違いを聞いてみた。
1500Mは、まだスピードを抑える時間があるが
800Mのほうは、ほぼずっとフルスピードに近く、辛いらしい。
そして、800Mが強い人は1500Mも強いらしい。
つまり1500Mは、人間であれば簡単にスピードを抑えられる。
競走馬は、騎手のいうことを聞けるか、聞けないかに左右される。
つまり「気性」が大切ということになる。
つまり距離適正は、スピード・スタミナの有無によってではなく、
気性に大きく左右される可能性が高いと考える。
例えば、サクラバクシンオーはスプリンターだが、
母の父に持つキタサンブラックはクラシックディスタンス向き。
このような、血統の不思議も、距離適性が「気性」で決まるのであれば納得できる。
牝系(ファミリーライン)が最重要
血統を考えるにおいて、最も重要なのは牝系の血統だと考える。
父系は種牡馬になるためには、現役時代に目覚ましい活躍をする必要がある。
そのため、極論ではあるが、どの種牡馬を選んでも強い馬に変わりない。
牝系は1年に1頭しか産めないので未勝利馬でも繁殖牝馬になる。
牝系は選択の余地があり、どの繁殖牝馬でも良いとはならない。
そういう意味で、牝系(ファミリーライン)が最重要と考える。
そして、繁殖牝馬が強い馬かではなく、牝系(ファミリーライン)に活躍馬が出ているかの方が重要。(もちろん繁殖牝馬自身が強い馬であることに越したことはないが)
なぜなら、潜性遺伝子による隔世遺伝や、遺伝子は持っているが発現しなかった可能性を考えると牝馬自身は競争能力が低くても、遺伝的には競争能力が高い可能性がある。
となると、牝系(ファミリーライン)に活躍馬が多くいるかは、競争能力を高める遺伝子を持つ可能性について、1つの指標になる。
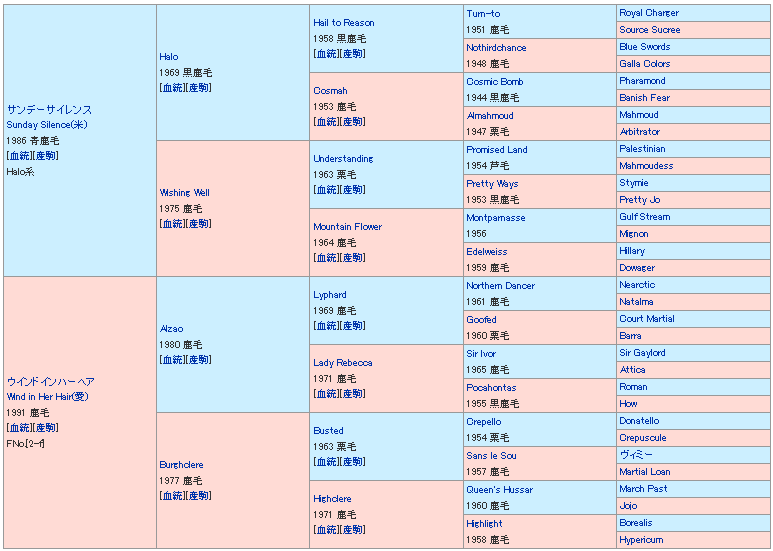
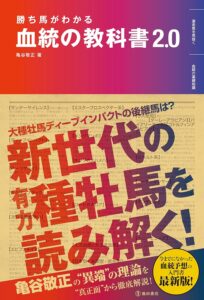

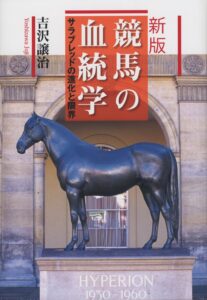

コメント